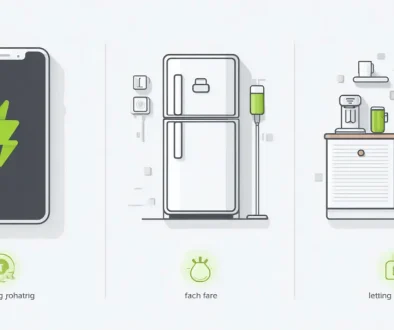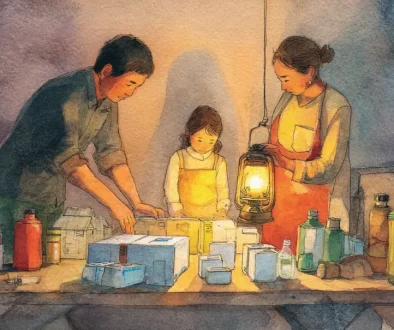帰宅困難者になったあなたへ|命を守るための行動セオリーと備え方
「家に帰れない…」そのとき、どう動く?
災害時の“帰宅困難者”に備えるための行動セオリー
大きな地震や豪雨、交通麻痺が発生したとき──
「電車もバスも止まった」「道路が寸断された」「会社から帰れない」
そうした“帰宅困難者”が都市部で多数発生するケースがあります。
この記事では、帰宅困難者になったときにどう行動すべきか、そしてその時に慌てないための備えについて、わかりやすく解説します。
帰宅困難者とは?
「帰宅困難者」とは、地震や風水害などの災害時に交通機関が停止・混乱し、自宅へ帰ることができなくなった人のことです。
特に以下のような条件で発生しやすくなります。
- 通勤・通学先が自宅から遠い
- 鉄道やバスへの依存度が高い都市部
- 夜間・雨天・寒冷期の災害時
- 地図や情報を持たず「とりあえず歩いて帰る」判断をしてしまう場合
2011年の東日本大震災では、首都圏で500万人以上の帰宅困難者が発生しました。
帰宅困難になったときの基本セオリー
「とにかく帰ろう」と思ってしまうのは自然ですが、それが危険を招くこともあります。
現在の災害対応では、以下のセオリーが推奨されています。
✅ 1. 無理に帰宅しない
- 災害直後は、建物の倒壊・余震・火災・落下物のリスクが高い
- 歩いて帰る途中に避難所やトイレ、給水場所がない可能性も
✅ 2. 一時待機を基本とする
- 会社・学校・商業施設などには、一時滞在スペース(帰宅困難者受け入れ体制)が整備されている場所も多い
- 行政や施設管理者の指示に従い、安全が確保されるまで待機
✅ 3. 正確な情報を得る
- SNSや噂ではなく、行政の防災無線・NHK・自治体の公式発表を確認
- 通信制限時はラジオ・災害用アプリ・掲示板が有効
「歩いて帰る」は最終手段と心得る
徒歩での帰宅は、体力的・安全面からも非常にリスクが高い行動です。
特に以下のような条件下では絶対に避けてください。
- 夜間や豪雨・寒波時
- ヒール靴や革靴など不適切な服装
- 高齢者・子ども・体調不良者が一緒の場合
- 地図・水・携帯バッテリーを持っていない場合
歩くとしても、3時間(約10km)以内の距離が現実的な限界とされています。
事前にできる備えと知識
✅ 持ち歩き防災セットの準備
- 携帯トイレ
- 携帯充電器(モバイルバッテリー)
- 小型ラジオ(AM/FM)
- 地図(紙)
- 簡易食・水(500ml×1本)
- 雨具・タオル・ライト・防寒シート
かばんに「薄く小さな1セット」を入れておくだけで安心感が変わります。
✅ 勤務先や学校の「帰宅困難者対策」を確認
- 一時滞在場所や備蓄の有無
- 家族との連絡方法(災害伝言ダイヤル171やLINEの既読確認など)
- 自宅付近と職場付近、両方の避難所を事前に調べておく
✅ 家族との連絡ルールを決めておく
- 電話がつながらない場合の連絡手段(LINE/SMS/災害用伝言板)
- 「先に帰る・待っている・避難所に行く」など、判断基準の共有
- 子どもが帰宅困難になる場合に備えて、学校との連絡方法とルールも再確認
まとめ:「帰らない勇気」が命を守る
帰宅困難になったとき、
大切なのは「焦って動くこと」ではなく、安全にとどまる選択です。
- 「歩いて帰る」は最終手段。まずは一時待機が基本
- 必要な情報を正しく得て、支援体制に従う
- 事前に“想定”しておくことが、自分と家族を守る鍵になる
「家族のために早く帰りたい」その想いが、
時に命を危険にさらすことがあります。
“帰らないことが、いちばんの思いやり”になることもある。
そんな心構えを、今日から持っておきましょう。